Archives【アーカイブ】
Talk at the 51st Annual Conference of the Japan Association for English Corpus Studies (JAECS) / 英語コーパス学会(JAECS)第51回大会にてトークを行いました
Associate Professor Sho Yokoi gave a talk titled “What a ‘stochastic parrot’ can do, and why it can do it” at the 51st Annual Conference of the Japan Association for English Corpus Studies (JAECS) held from September 2nd to 3rd.
9月2日から3日にかけて開催された英語コーパス学会(JAECS)第51回大会にて、横井祥准教授が『「確率的なオウム」にできること、またそれがなぜできるのかについて』のタイトルでトークを行いました。

2025.7.24 MiCS: Mr.Yuya Matsumura, Mr. Yusuke Shibui / MiCS(みちのく情報伝達学セミナー):松村優也氏, 澁井雄介氏ご講演
Mr. Yuya Matsumura, Mr. Yusuke Shibui from LayerX, Inc. gave a talk entitled “Bakuraku’s vision of fully autonomous business operations and the foundational technologies—including workflow auto-generation—required to realize agentic workflows.” (MiCS)
株式会社LayerXの松村優也氏、澁井雄介氏に、「バクラクの目指す“業務の完全自動運転” と、その実現に向けて必要な技術」および「Agentic Workflowを実現するワークフロー自動生成と基盤技術」という表題でご講演いただきました。(みちのく情報伝達学セミナー)


2025.7.3 MiCS : Mr.Aozora Inagaki, Mr.Haruki Nagasawa and Mr.Yuna Suzuki / MiCS(みちのく情報伝達学セミナー):稲垣青空氏、干飯啓太氏、長澤春希氏、鈴木裕奈氏ご講演
Mr.Aozora Inagaki, Mr.Keita Hoshii, Mr.Haruki Nagasawa, and Ms.Yuna Suzuki from CyberAgent, Inc. gave a talk entitled “The Social Implementation of ML Technologies at CyberAgent: What Changes and What Remains the Same with Generative AI” (MiCS)
株式会社サイバーエージェントの稲垣青空氏、干飯啓太氏、長澤春希氏、鈴木裕奈氏に、「サイバーエージェントにおけるML技術の社会実装 ~生成AIで変わるもの・変わらないもの~ 」という表題でご講演いただきました。(みちのく情報伝達学セミナー)


2025.6.19 MiCS: Prof.JinYeong Bak / MiCS(みちのく情報伝達学セミナー): JinYeong Bak准教授ご講演
Prof. JinYeong Bak from Sungkyunkwan University gave a talk entitled “Enhancing Memory in Neural Networks: Memory Retention, Efficient Adaptation, and Self-Training for Reasoning” (MiCS)
成均館大学校のJinYeong Bak准教授に、「Enhancing Memory in Neural Networks: Memory Retention, Efficient Adaptation, and Self-Training for Reasoning 」という表題でご講演いただきました。(みちのく情報伝達学セミナー)
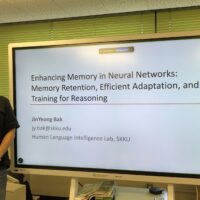

2025.5.08 MiCS: Prof.Timothy Baldwin / MiCS(みちのく情報伝達学セミナー):Timothy Baldwin教授ご講演
Prof. Timothy Baldwin from MBZUAI gave a talk entitled “Fact-checking LMs: the Truth, the Whole Truth, and Nothing but the Truth.” (MiCS)
MBZUAIのTim Baldwin教授に、「Fact-checking LMs: the Truth, the Whole Truth, and Nothing but the Truth. 」という表題でご講演いただきました。(みちのく情報伝達学セミナー)


Research talk at LLM-jp / LLM 勉強会
Second year master’s student Momoka Furuhashi gave a research talk “Is the use of checklists effective in the automatic evaluation of generative tasks?” at LLM-jp on 3/25.
3/25に開催された LLM 勉強会 にて、修士2年の古橋萌々香さんが「生成系タスクの自動評価においてチェックリストの使用は有効なのか?」という題で研究発表を行いました。

Talk at Statistical Physics 12th Symposium / 統計物理学懇談会(第 12 回)にてトークを行いました
Associate Professor Sho Yokoi gave a talk titled “Natural Language as a Point Cloud in High-Dimensional Space” at Statistical Physics 12th Symposium held on March 24 and 25.
3月24日、25日に開催された統計物理学懇談会(第 12 回)にて、横井祥准教授が「高次元空間上の点群としての自然言語」のタイトルでトークを行いました。

Talk at 8 Universities Jointly Held Informatics for all by all / 8大学同時共同開催 情報学 for all by all にてトークを行いました
Assistant Professor Reina Akama gave a talk titled “Why Informatics Now?” at 8 Universities Jointly Held Informatics for all by all held on March 16.
3月16日に開催された8大学同時共同開催 情報学 for all by all にて、赤間怜奈助教が「いま、なぜ、情報学?」のタイトルでトークを行いました。

2025.3.05 MiCS: Mr.Tatsuro Inaba / MiCS(みちのく情報伝達学セミナー):稲葉達郎氏ご講演
Mr. Tatsuro Inaba from Kyoto University gave a talk entitled “How LLMs Learn: Tracing Internal Representations with Sparse Autoencoders.” (MiCS)
京都大学の稲葉達郎氏に、「スパースオートエンコーダを用いたチェックポイント横断分析」という表題でご講演いただきました。(みちのく情報伝達学セミナー)


Talk at Humanities+ 3rd Research Meeting: “Vectors, Words, and Meanings” / ヒューマニティーズ+ 第3回研究会「ベクトル・言葉・意味」にてトークを行いました
Associate Professor Sho Yokoi gave a talk titled “What a ‘stochastic parrot’ can do, and why it can do it” at Humanities+ 3rd Research Meeting: “Vectors, Words, and Meanings” held on March 4th.
3月4日に開催されたヒューマニティーズ+ 第3回研究会「ベクトル・言葉・意味」にて、横井祥准教授が『「確率的なオウム」にできること、またそれがなぜできるのかについて』のタイトルでトークを行いました。

Talk at NINJAL Launch Ceremony and First Research Meeting of the Advanced Language Science (E3P) Research Center / 国立国語研究所次世代言語科学研究センター開所式にてトークを行いました
Associate Professor Sho Yokoi gave a talk at NINJAL Launch Ceremony and First Research Meeting of the Advanced Language Science (E3P) Research Center held on March 3rd.
3月3日に開催された国立国語研究所次世代言語科学研究センター開所式及び第1回研究会にて、横井祥准教授が『コーパスを丸呑みしたモデルから言語の何がわかるか』のタイトルでトークを行いました。

2025.2.18 MiCS: Prof. Pontus Stenetorp / MiCS(みちのく情報伝達学セミナー):Pontus Stenetorp教授ご講演
Prof. Pontus Stenetorp from University College London (UCL) gave a talk entitled “Multilingual Language Model Pretraining using Machine-translated Data” (MiCS)
ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン (UCL)のPontus Stenetorp教授に、「Multilingual Language Model Pretraining using Machine-translated Data」という表題でご講演いただきました。(みちのく情報伝達学セミナー)


2025.1.27 MiCS: Mr. Jan Buchmann / MiCS(みちのく情報伝達学セミナー):Jan Buchmann氏ご講演
Mr. Jan Buchmann from Technical University of Darmstadt gave a talk entitled “NLP for Long, Structured Documents” (MiCS)
ダルムシュタット工科大学のJan Buchmann氏に、「NLP for Long, Structured Documents」という表題でご講演いただきました。(みちのく情報伝達学セミナー)


Talk at the 57th Annual Meeting of the Philosophy of Science Society, Japan / 日本科学哲学会第57回(2024年度)大会にてトークを行いました
Assistant Professor Sho Yokoi gave a talk at the 57th Annual Meeting of the Philosophy of Science Society, Japan, from November 30th to December 1st.
横井祥助教が11月30日から12月1日かけておこなわれた日本科学哲学会第57回(2024年度)大会にて開催されたワークショップ『AIから考える言語・知性・科学』に登壇しました。

2024.11.28 MiCS: Dr.Masatoshi Suzuki / MiCS(みちのく情報伝達学セミナー):鈴木正敏氏ご講演
Dr. Masatoshi Suzuki from Studio Ousia / Center for Data-driven Science and Artificial Intelligence Tohoku University gave a talk entitled “My Answers to challenges in Japanese Question Answering -10 Years in Tohoku NLP-“.(MiCS)
株式会社 Studio Ousia /東北大学データ駆動科学・AI教育研究センターの鈴木正敏氏に、「日本語質問応答研究に対して私が出した「答案」〜Tohoku NLPで生きた10年〜」という表題でご講演いただきました。(みちのく情報伝達学セミナー)


2024.10.24 MiCS: Mr. Joe Stacey / MiCS(みちのく情報伝達学セミナー):Joe Stacey氏ご講演
Mr. Joe Stacey from Imperial College London gave a talk entitled “Atom-based approaches to creating interpretable NLI models” (MiCS)
インペリアル・カレッジ・ロンドンのJoe Stacey氏に、「Atom-based approaches to creating interpretable NLI models」という表題でご講演いただきました。(みちのく情報伝達学セミナー)


2024.9.27 MiCS: Mr. Manabu Yamaguchi and Dr. Kazuaki Hanawa / MiCS(みちのく情報伝達学セミナー):山口学氏、塙一晃氏ご講演
Mr. Manabu Yamaguchi and Dr. Kazuaki Hanawa from Kodansha Ltd. gave a talk entitled “About Kodansha’s New Challenges.” (MiCS)
株式会社講談社の山口学氏、塙一晃氏に「講談社の新しいチャレンジについて」という表題でご講演いただきました。(みちのく情報伝達学セミナー)


2024.8.22 MiCS: Dr.Tatsuki Kuribayashi / MiCS(みちのく情報伝達学セミナー):栗林樹生氏ご講演
Dr. Tatsuki Kuribayashi from MBZUAI gave a talk entitled “Natural Language Processing for Answering Fundamental Questions about Language.” (MiCS)
MBZUAIの栗林樹生氏に、「言語の根本的な問いに答えるための自然言語処理」という表題でご講演いただきました。(みちのく情報伝達学セミナー)


2024.8.22 MiCS: Dr.Natsuko Nakagawa / MiCS(みちのく情報伝達学セミナー):中川奈津子氏ご講演
Dr. Natsuko Nakagawa from Kyushu University gave a talk entitled “Unsolved Problems in Linguistics: Change, Mutation, and Extra-linguistic Meaning.” (MiCS)
九州大学 の中川奈津子氏に、「言語学の未解決問題: 言語変化、変異、言外の意味」という表題でご講演いただきました。(みちのく情報伝達学セミナー)


2024.8.20 MiCS: Mr.Hiroyuki Deguchi / MiCS(みちのく情報伝達学セミナー):出口祥之氏ご講演
Mr. Hiroyuki Deguchi from NAIST gave a talk entitled “Minimum Bayes Risk Decoding for High-Quality Text Generation Beyond High-Probability Text.” (MiCS)
NAISTの出口祥之氏に、「Minimum Bayes Risk Decoding for High-Quality Text Generation Beyond High-Probability Text」という表題でご講演いただきました。(みちのく情報伝達学セミナー)
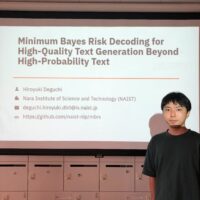

これ以上は記事がありません
これ以上は記事がありません

